 |
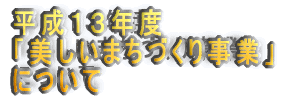 |
 |
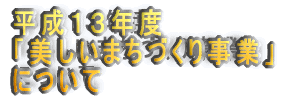 |
平成13年度「地域資源を活かした美しいまちづくり事業」にかかる
わたしが見つけたセニック・ポイント審査会感想等について
辻 みどり
この事業の趣旨を説明され審査員にという打診を受けたとき、即座に引き受けたいと思いました。私自身、昨年4月に出版された共著『グローバリゼーションと地域』(八朔社)の第16章として「文化的環境としての地域文化の創生―メディアトライブ形成による表象空間の再編成を中心に―」を書いたとき、都会の消費文化の欠如を嘆くのではなく、地方の空間に既存の表象に対して内発的な意味付けを行い、都市文化ヘゲモニーから脱却できるような文化的価値を提起しなければならない、というようなことを書いたのですが、今回の事業は、まさにその実践に相当すると思われたからです。
自然が産みだす美しい景観は、県南地方のいたるところにあるのでしょうが、気づかれず、情報にも載らなければ、埋もれた資源として終わってしまいます。認知と情報化によって、文化資源として機能するようになりますし、それにも増して、地域住民の安らぎの場となりプライドの源となるはずです。
今回の事業の企画は、そういう点では、行政側の高い見識と実行力を示す好例となりましたが、その趣旨の徹底と認識の普及は難しく、審査員の間ですら、冒頭のレクチャーと実際の選出作業の過程で、時間をかけてやっと浸透したように見受けられました。
審査の過程では、他所に類を見ない美観・奇観ばかりでなく、農作業の合間に腰をさすりながら身体を起こしたときに目に入る那須連峰の光景や、まるで軽井沢を思わせるような木漏れ日の美しい散歩道といった光景も、地域に暮らす人々の生活/人生のドラマの一ページを見るようで、さりげない景色に意味が付与され、まことに今回の趣旨にかなったものとして、眼にとまりました。
大賞受賞作は、上記のような生活との関わりに加えて、水源の地という県南の資源のアイデンティティに合致することから、文句ない選択と思われますが、他の入賞作品、ベスト30作品にしても、撮影者の視点の位置及びていねいなコメントを要求したことにより、単なる名所旧跡集成に留まらず、また単なるフォトコンテストに終わらない、趣旨にかなった啓蒙事業ができたかと思います。
このコンテストの結果発表によって啓発される人々が、さらなる文化資源の掘り起こしを続けるよう支援し、また時勢に応じて新しいセニック・ポイントが掘り起こされることを期待して、恒常的に投稿できる場を確保することが、望まれると思います。こういった事業を支える技術的側面として、インターネット上のホームページ構築を自在に行う人材が、キーパーソンであるようにも思えました。あとは、この卓越したホームページの存在をパソコン雑誌で一度紹介すること(私は自分の講義で学生たちにURLを紹介してしまいました)、さらにホームページに外国語版も作れば、国内観光客のみならず、W杯で来日する予定の外国人観光客をひきつけるような展開も期待できることでしょう。