 |
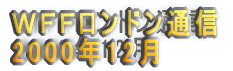 |
 |
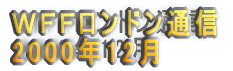 |
すっかりご無沙汰していますが,皆さまお変わりなくお過ごしでしょうか。ロンドンは今,街も人もクリスマスに向けて,全てのエネルギーを投入しようとしているようです。
今年のカレンダーで言えば,22日の土曜日から始まり26日のボクシングデーまでがクリスマス・ホリデーとなり公共機関が休業します。「クリスマスは欧米では宗教行事」という常套句通り,家族単位ではイヴに教会のミサに出かけるスケジュールが組み込まれたり,それ以前にも,クリスマス向けのチャリティ(慈善)のバザーやディナーが頻繁に開かれるようになります。人々は突然のように宗教やチャリティの精神を前面に押し出し,1年分の精神のお清めをすませるかのようです。
しかし同時に,クリスマスは歳末商戦に他ならないという感があります。個々の家族単位で祝うばかりでなく,親族の中で誰かの家庭に一同が集まり,集まる親戚や友人のそれぞれに対して,一人一人がまがりなりにもプレゼントを準備するため,とんでもない数のプレゼントが準備されることになりますし(日本で言えば,子どもたちがお年玉をもらうチャンスと同じような位置付け),また「クリスマスだから」という根拠が免罪符となり,普段の質素・倹約が吹っ飛ぶほどの,贅沢,浪費,非日常的行為が,問われることなくまかり通るようです。
実際,10月頃からクリスマス・プレゼント用の様々なメール・オーダー・カタログ(日本の御歳暮ギフトセットのような,クリスマス・プレゼント用セットが準備されています)が届き始め,デパートのハロッズにはクリスマス・ツリーに下げる飾りのコーナーが準備されました。12月に入った現在,繁華街ではクリスマス用の電飾が光の屋根のように車道の上を覆い尽くし,女性衣料品店にはゴージャスなパーティ用のドレスが並び,買物客の気分はいやおうなく盛り上げっていくという按配です。
ロンドンはインド,アラブ諸国,パキスタン,トルコ,中国,ギリシアなど,多様な人種・民族・国籍・言語の住人を抱え,それぞれの背景となる食生活など生活文化が商品や店舗を媒介として,混在しています。
英国では今,クリスマスに向けて,人々のエネルギーが集中していくところです。日本で言えばお歳暮以降の歳末商戦というところでしょうか。親族や友人の家で開かれるディナーやパーティのためのツリー用装飾や贅沢な食品に豪華なドレス,持参するプレゼント用のギフトセット等が展示され,消費者の目を惹きつけています。「クリスマスだから」という言葉が免罪符となり,宗教行事及び慈善の美名のもとに,1年分の過剰な贅沢,浪費,非日常的行為が問われることなくまかり通るようです。少し意地悪な表現でしょうか。
こちらでの生活に慣れるに連れて,ロンドンの街では人種や民族,宗教や国籍も言語も多様な人々が共存している様子が見えてきました。薬屋やコンビニ的雑貨屋はインド人が多く,クリーニング屋はパキスタン人が多いなど,職種と居住地域のすみわけが階層構造につながる危惧があるのですが,彼らの民族衣装や宗教行事,レストラン,食料品店などが否応なく日常的に視野に入り地域の空間を共有するという意味で,多文化共生の実態が先行しています。また,彼らが持ちこんだ独特な食料品や生活雑貨が,周辺に居住する地域住民に浸透し,古くから居住している英国人の生活文化を変容させています。
現在,ミュージカル「王様とわたし」が上演されており,リアルさを狙って,タイ人の役にアジア人を出演させています(アジア系というだけで,実はフィリピン系,コリア系アメリカ人だったり日本人だったりします)。しかし,英語の発音がおかしいといって笑い者にするギャグなど,観客にもアジア人がいるし,ステージ上のリアルなアジア人を笑うわけにもいかず,中途半端で消化不良になってしまっていました(作品の意図に関しても,ヴィクトリア朝の女性家庭教師が,自分はコルセットで身体を異常に締めつけられながら,タイ人の王様に民主的でないと説教するシーンなどは違和感があり,いくらタイ料理が流行りだからといって,上演する現代的意味を見出せないのですが)。
一方,19世紀末の日本ブームの中で一世を風靡したギルバート&サリバンの「ミカド」では,出演者全員が西欧人で黒髪に顔を白塗り,英国紳士や淑女の衣服の上にキモノ風の上着をはおり帯を締めるという奇妙な衣装でした。作品は日本が舞台で,帝の恋愛禁止令に反した息子と恋人,政府高官が繰り広げる喜歌劇なのですが,実際の意図は当時の英国王室や政府の諷刺にあります。
日本人というのは19世紀末にはほとんど非日常的な生き物でも,現代英国には,現実の日本人が多数棲息しており,リアルに演じれば,ストレートな日本人諷刺になりかねないところを,わざとらしい衣装で虚構の意図を観客に意識させ,心置きなく笑いを引き出すことに成功していました。ロンドンでは多文化共生が,文化の生産/消費の前提として認識される時期に入ったようです。
しかし「英国人」とは誰かという疑問もあります。ホームステイをしている家庭の夫は英国人ですが,妻は米国人,子どもたちは外見は白人のアングロサクソンで英国国籍ですがアメリカ的食習慣を身につけています。またロンドン大学には外見は日本人で日本生まれですが米国生活が長く,母語が米語,文化背景はアメリカ文化という学生さんもいます。
「国際結婚」を研究している客員研究員仲間の話では,英語圏では"Mixed Marriage"(雑婚)という概念でくくり,国籍というより異なる宗教,異なる人種,異なる民族といった要素が前面に打ち出されるということですが,地域住民という集団に関しても同じことが言えそうです。移民の多いブラジル出身で,インド系の母方とイタリア系の父方という両親から生まれたマリアは浅黒い肌・黒髪に青い瞳という珍しい組み合わせの容姿でしたが,彼女に言わせると「英語学校で見かける日本人学生は,みんな同じような容姿で(無理に茶髪にしているし)びっくりした」という認識になるのです。
日本で暮らしていると,自分の日本人としてのアイデンティティに疑問も抱きませんでしたが,「このむかつく…・アジア人め」とののしられた時には,侮蔑的表現にショックを受ける以前に,「アジア人」というカテゴリーで呼ばれたことも驚きでした。また白粉を買いに行ったファッションビルで,白人向けの大理石のように白い白粉しか品揃えがなかったとき「ああ私の肌は黄色いんだ」と認識し,その店の主な購買客とは違う人種なんだと実感しました。
西欧的な服を着て,西欧的な食事を食べ,西欧的な音楽を聞いている私たちはいったい何なのでしょう。肌の色と使用言語を問われたとき,アジアー日本が浮上してきますが,多文化共生の時代が
年配の白人でアングロサクソンの英国人住民の中には,多文化共生の時代になって,古き良きモラルやマナーが崩れてきたことを嘆く声も聞かれます。英国というとすぐに思い出された,地下鉄のエスカレーターで右側に立ち急ぐ人のために左側を空ける習慣や,乗り物の中で老人に席を譲るマナー,個々のモラルを前提として規制を設けずに済ませてきた緩やかな制度などが機能しなくなってきているというのです。
少し前に、おしろいが無くなりかけ,替わりを買いに出かけたのですが,ボンドストリート(日本で言えば銀座か日本橋あたり)のファッションビルに入り、化粧品コーナーでサンプルを出してもらったところ、どれも皆、白いのです。4色あるサンプルは多少色味が違うのですが、それにしても人形の肌のような白さに驚き、ああ自分は黄色人種なんだという事実を思い知らされました。
別の日に、日本人客も行きそうな大手のデパートに行って見たところ,ベージュ系のバリエーションが見つかりました。店員さんも人種は様々いるのですが,その時対応してくれた店員さんは金髪に青い目の女性で、私の皮膚にサンプルをつけながら説明し始めたのですが「この白粉の色なら,あなたの肌の色が…」と言って,言葉をとぎらせました。「イエロー」と言ったら黄色人種への侮蔑語にあたります。本人は肌の色の相違という事実の表現のつもりでも,聞く側にとっては人種差別的なニュアンスを持つ表現に転じかねない,微妙な瞬間でした。私もはっとし,二人が目を宙にさまよわせて沈黙が続いた息詰る数秒の後,彼女が言葉を続けました。「はちみつ色なのでぴったりですわ」ふ〜っ。プロの機転に,ため息をついた一瞬でした。